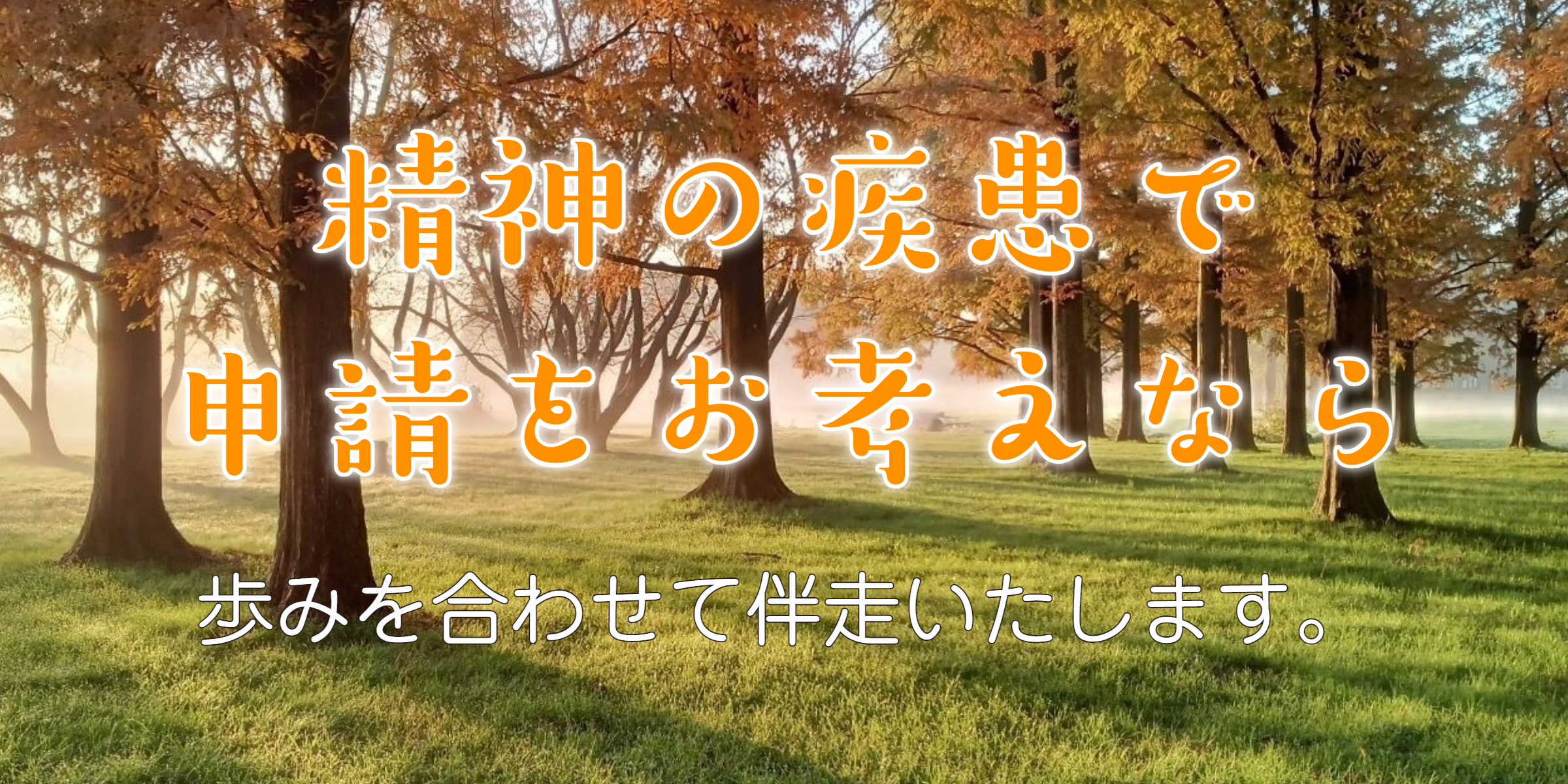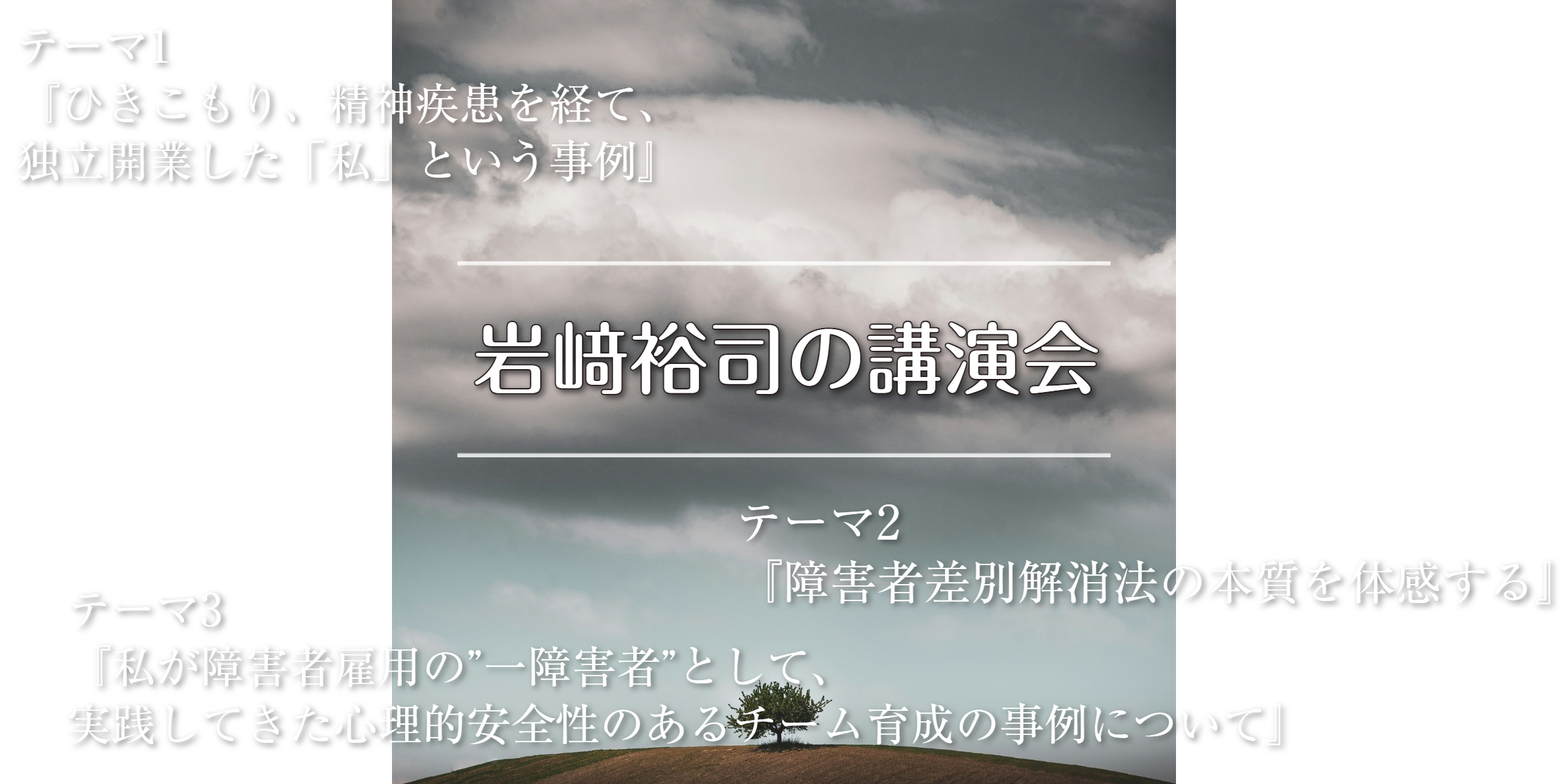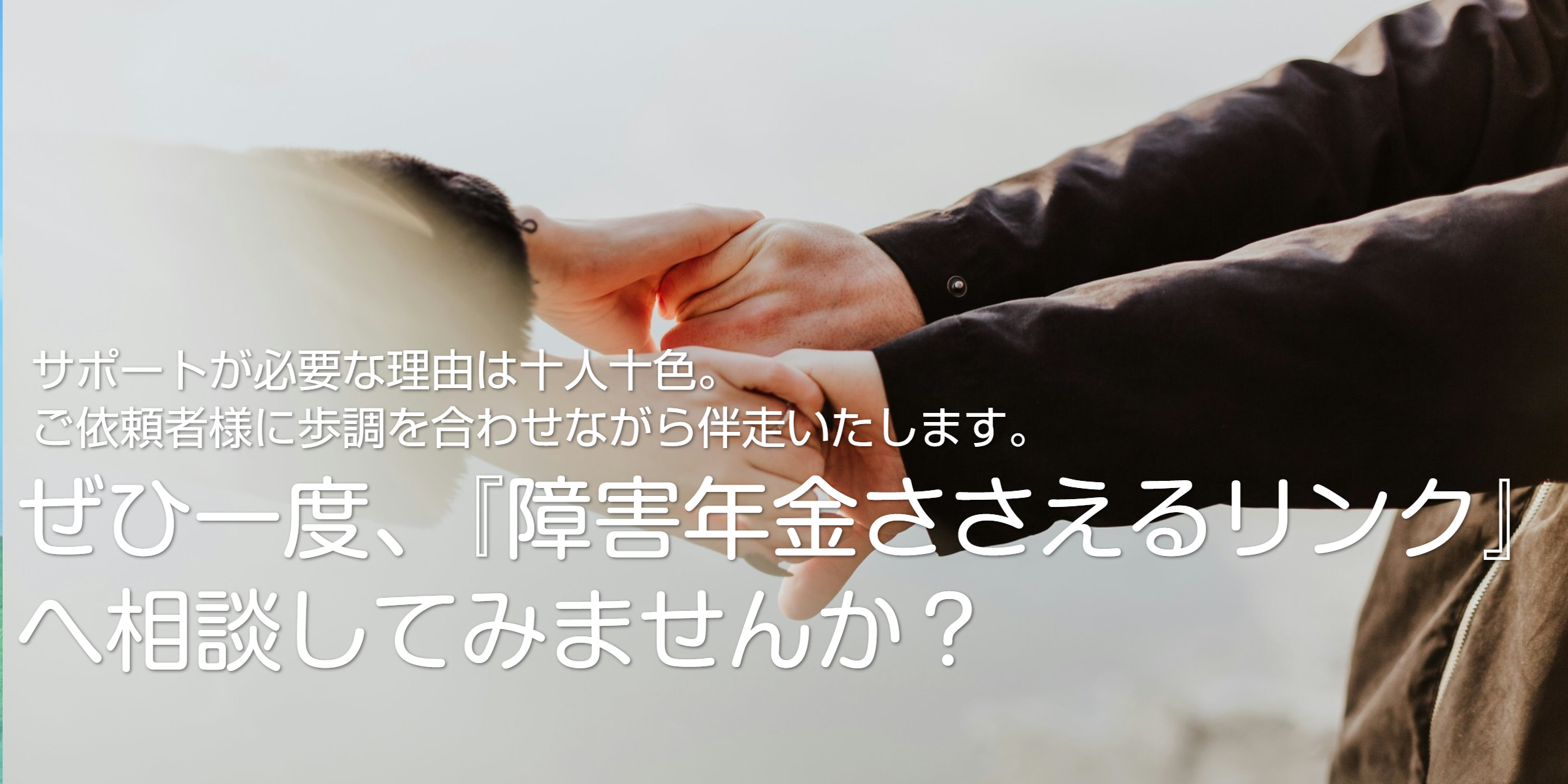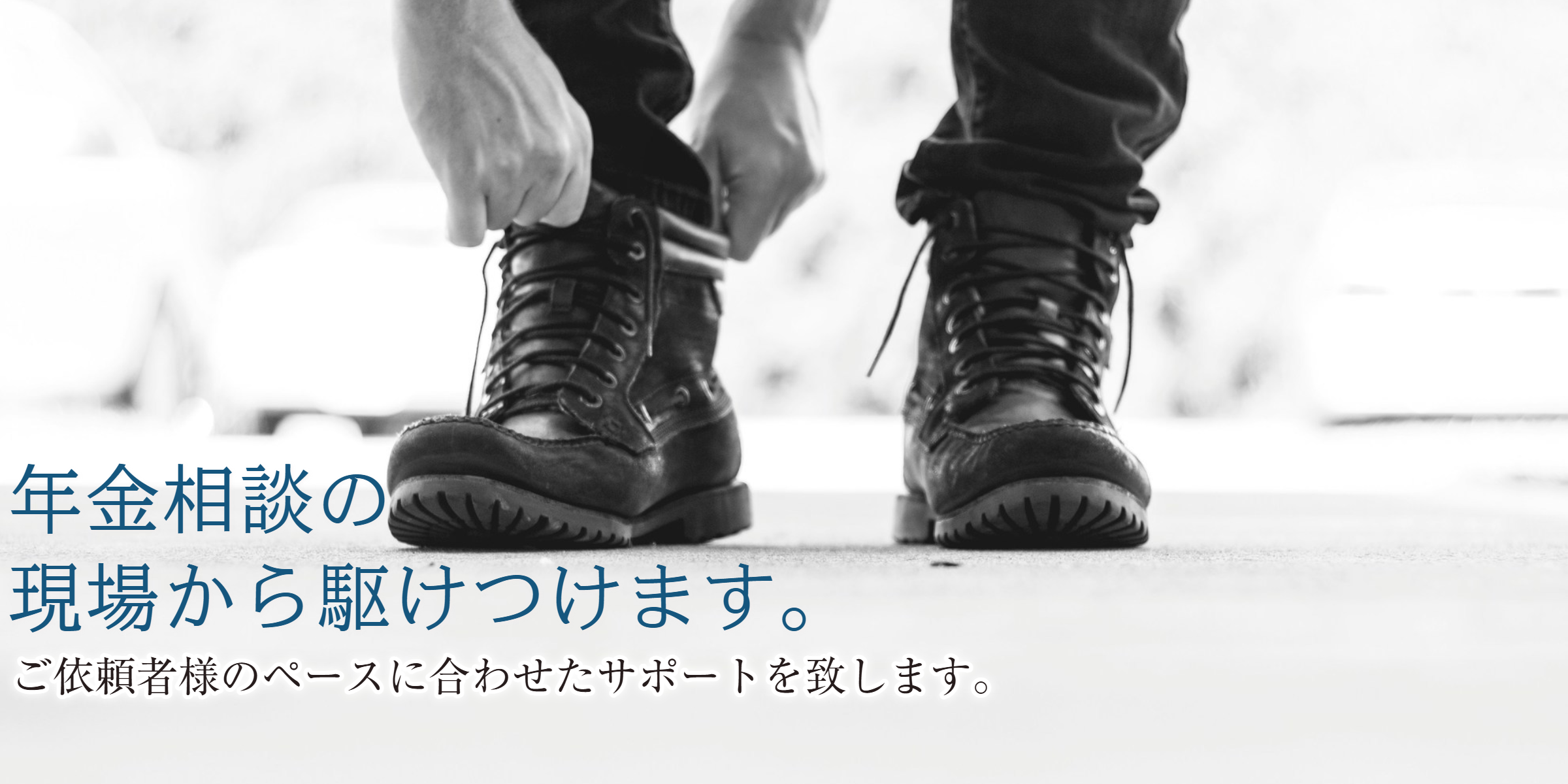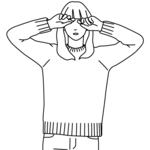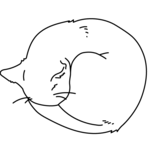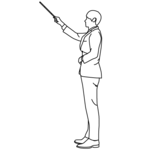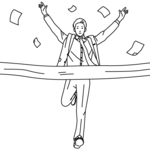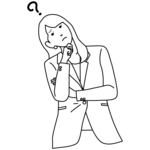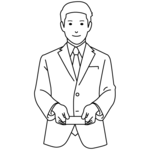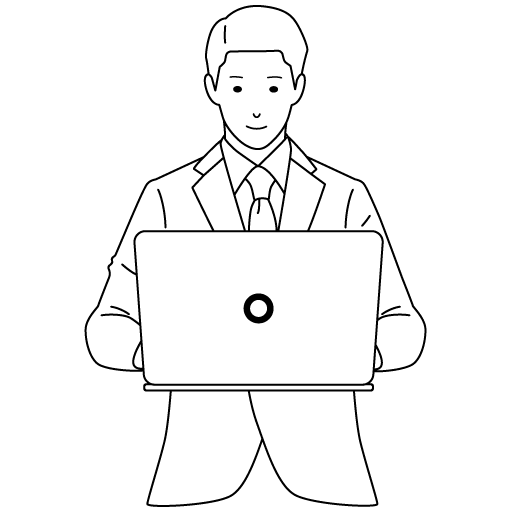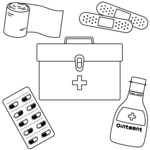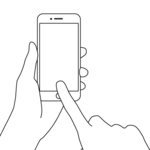運営:社労士Officeボクマクハリ(東京都葛飾区東水元)
受付時間
(年中無休)
【葛飾区】障害年金専門の社労士
障害年金ささえるリンク
葛飾区にある障害年金ささえるリンクへようこそ。当事務所は葛飾区を中心に全国で、
障害年金申請代行をご提供しています。
うつ病や統合失調症、発達障害、知的障害など精神の申請を多く手掛けています。
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
障害年金申請代行
障害年金ささえるリンクでは障害年金申請において、相談・申請代行業務を承っております。
- かかりつけのお医者さまに障害年金受給をすすめられた方
- 障害年金を申請し不支給となってしまった方
- 手続きのストレスから解放されたいとお考えの方
など、お気軽にご相談ください。
葛飾区で障害年金の申請を社労士に依頼するメリット

年金事務所勤務の「年金特別アドバイザー・社労士」なので、生きた知識と経験でサポート
安心の年金相談は、年金事務所で勤務している、経験豊富な社労士がお手伝いします!
日々の実務で培った知識と経験を活かし、的確なアドバイスを提供します。行政との連携も強化し、お客さまのニーズにマッチした解決策を迅速にご提案します。
更に、障害年金専門の研究部会にも所属し、幅広い専門知識を持つプロフェッショナルとのネットワークも活かします。信頼と安心のパートナーとして、あなたの年金に関する不安を一緒に解消しましょう!

話しやすい、不安にさせない、
当事者意識のある社労士です
当事者の立場から、あなたの声に耳を傾けます。足かけ7年のひきこもりや精神疾患の経験を持つ社労士が、当事者の視点から丁寧に対応します。
米国のラップアラウンド・ユースピアサポーター養成プログラムを修了し、葛飾区、北区、目黒区などの居場所事業にも関わっています。自らも定期的にスーパービジョン(カウンセリング)を受けて自己状況を調整し、いつでもあなたをサポートする体制を整えています。安心してお任せください。

ご自宅又はお近くまで伺います
お自宅又はお近くまで伺います。遠方の方は電話やLINE、zoomなどでお話を伺うことも可能です。障害年金は書類審査ですので、葛飾区以外、もちろん全国のお客様の申請も承っております。
※出張料金は、東京都葛飾区金町駅より1時間半圏内無料。

ご相談者様や、そのご家族に、
「ホッと一息」を提供したいです。
こんにちは、障害年金ささえるリンクの岩﨑 裕司 (いわさき ゆうじ)です。サイトへのご訪問ありがとうございます。
当事者、専門家両方の視点で丁寧にサポート致します。
ご依頼者のご自宅やお近くまで伺わせて頂いております。
お気軽にお問合せ・ご相談ください。
かかりつけ医のような社労士でありたい
葛飾区でのご相談事例
神経症で障害年金が認定されたケース
葛飾区にお住いのお母さまからのご相談でした。お子様が10代の時に発症し、初診日のカルテもないとのことでした。初診の病院に連絡しパソコン上にも記録は残っていないか確認頂き、任意の証明書という形で初診日証明を行いました。また、20歳の認定日前後3か月に受診がなく、20歳4か月のところで入院がありましたので、こちらの診断書も用意しました。医師に協力頂き認定日の状況と同一であったかどうかの推察を頂き、意見書を添付しました。障害年金は書類審査のため、1日でも遅れればダメなことが殆どですが、過去に認定されたこともあり、可能性があれば診断書を取得しています。
また、今回は障害年金対象外の神経症に該当する為、精神障害の病態があるかどうかが重要になりました。認定日、直近両医師の協力を得て、統合失調症の病態があることが確認でき請求することが出来ました。認定日は却下されてしまいましたが、事後重症で認定されました。
親亡き後の心配を少しでも和らげることが出来た1例だったと思います。引き続きサポートすることくをお約束いたしました。
障害年金の疾病一覧・精神障害
統合失調症で障害年金を申請するケース
統合失調症は、幻覚や妄想といった精神病症状や意欲が低下し、感情が出にくくなるなどの機能低下、認知機能の低下などを主症状とする精神疾患です。
日本の統合失調症の患者数はおよそ80万人程度といわれており、世界各国の報告によると100人に1人弱がかかるという比較的頻度の高い病気であると考えられています。多くは10歳代後半から30歳代頃に発症するといわれています。
統合失調症の原因は明らかになっていません。脳に情報を伝える機能の変化や遺伝、環境などが複雑に関係しているといわれています。あくまで仮設ですが、もともと統合失調症になりやすい要因を持った人に進学や就職、結婚など環境の変化や人間関係の大きなストレスや緊張が発症のきっかけになるのではないかと考えられています。
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他 妄 想 ・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の 援助 が必要なもの | ||
| 2級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他 妄 想 ・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの | ||
| 3級 | 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他 妄 想 ・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの | ||
2 統合失調症 、統合失調症 型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められる ものが多い。しかし、罹 病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ 気分(感情)障害 は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すもの である。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、 統合失調症等とその他 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
3 日常生活 能力 等の判定に当たっては 、身体的機能及び精神的機能 を考慮の上 、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活 能力 が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通 の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
4 人格障害は、原則として認定の対象と ならない。
5 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は 気分(感情)障害 に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分 のどの区分に属す病態であるかを 考慮し判断すること。
うつ病で障害年金を申請するケース
双極性障害は、躁そう状態または軽躁状態とうつ状態とを反復する精神疾患です。“躁うつ病”と呼称される場合もありますが、うつ病とは別の病気です。
激しい躁状態を伴う場合を“双極I型障害”、生活に著しい支障がない程度の軽躁状態(軽度の躁状態)を伴う場合を“双極II型障害”といいます。躁状態あるいは軽躁状態のときは自身が病気であることに気付けない場合もあり、うつ状態だけが注目されがちであるため、双極性障害でありながらうつ病と診断されてしまう人も少なくありません。
躁状態による問題行動や、うつ状態による抑うつ気分・何をしても楽しいと思えない状態により社会生活に支障が生じることもあるほか、自殺率が高いことも知られています。主に20歳代で発症することが多く、有病率は1%程度で頻度に性差はないといわれています。調子のいいときと悪い時を繰り返す病気のため、現症のみによって認定するのではなく、「症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を考慮する」とされています。
1 各等級 に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 気分(感情)障害 に よるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の 援助 が必要なもの | ||
| 2級 | 気分(感情)障害 に よるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの | ||
| 3級 | 気分(感情)障害 に よるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、そ の病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの | ||
2 統合失調症 、統合失調症 型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められる ものが多い。しかし、罹 病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ 気分(感情)障害 は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すもの である。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、 統合失調症等とその他 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
3 日常生活 能力 等の判定に当たっては 、身体的機能及び精神的機能 を考慮の上 、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活 能力 が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通 の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
4 人格障害は、原則として認定の対象と ならない。
5 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は 気分(感情)障害 に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分 のどの区分に属す病態であるかを 考慮し判断すること。
発達障害で障害年金を申請するケース
広汎性発達障害は、小児自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害を包括する用語です。この疾患は、先天的な脳の機能障害や中枢神経系の発達に関わる疾患とされています。広汎性発達障害を持つ人は、「対人関係の障害(社会性の障害)」「コミュニケーションの障害(言語機能の発達障害)」「イマジネーションの障害(こだわり行動や興味の偏り、固執性)」の3つの特徴的な障害を示すことがあります。知的障害を伴わない場合、高機能群の広汎性発達障害とされ、それでも自閉性を示します。
知能指数が高くても、社会的な行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通に困難が生じることがあります。そのため、日常生活において著しい制限を受けることがあります。
広汎性発達障害は、障害年金の対象となる疾患です。通常、低年齢で発症するため、初診日は20歳未満であることが一般的です。ただし、知的障害を伴わない場合には、発達障害の症状によって初めて医師を受診した日が20歳以降であった場合、その日が初診日と見なされます。
1 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
2 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。また、発達障害と その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
3 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、 知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、 初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日 とする。
4 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの | ||
| 2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため 、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの | ||
| 3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの | ||
5 日常生活能力等の判定に当たっては、 身体的機能及び精神的機能を考慮の上 、社会的な適応性の程度 によって判断 するよう努める。
6 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働 に従事している者については、 その療養状況を考慮するとともに、 仕事の 種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
知的障害で障害年金を申請するケース
知的障害は、発達期(一般的には18歳まで)に知的機能の障害が現れ、その結果として日常生活に持続的な支障が生じるため、特別な援助を必要とする状態を指します。
知的障害の発症は通常18歳未満であるため、厚生年金に加入している場合を除き、20歳未満の障害年金を請求することになります。この場合、保険料の納付要件は適用されません。障害認定日は、本人が20歳の誕生日を迎えた日、または初診日から一年六ヶ月後の遅い方が適用されます。
知的障害の認定には、「知能指数だけでなく、日常生活の様々な側面における援助の必要性を総合的に考慮する」という原則が定められています。例えば、自己の世話や他者とのコミュニケーションなど、日常生活での援助がどれほど必要かが判断の根拠となります。
さらに、障害年金の請求手続きを行う前に、社会保険労務士に相談することをお勧めします。これによって、働いている場合でも障害年金の支給が妨げられないよう工夫して請求を行います。
1 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
2 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって 、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常 生活が困難 で常時援助を必要とするもの | ||
| 2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を 行うのに援助が必要であって 、かつ、会話による意思 の疎通が簡単なものに限られるため、 日常生活に あたって援助が必要なもの | ||
| 3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの | ||
3 知的障害 の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。また、知的 障害と その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
4 日常生活能力等の判定に当たっては、 身体的機能及び精神的機能を考慮の上 、社会的な適応性の程度 によって判断 するよう努める。
5 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働 に従事している者については、 その療養状況を考慮するとともに、 仕事の 種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
障害年金の無料セミナー開催中
かかりつけ社労士 連携中
新着情報
| 居場所事業(北区、目黒区、新宿区、葛飾区など)の最新予定は下記から |
|---|
| 居場所事業(葛飾区)の最新予定は下記から |
|---|
| 2024/03/13 | ホームページを公開しました |
|---|
お客さまの声(葛飾区)
問題がスムーズに解決します。
非常にスピーディに対応頂いたおかげで、自分で手続きをするよりも早く、認定を受けることが出来ました。
対応が早く、誠実だと感じました。
人柄も良く、親切かつ丁寧に一つ一つを分かりやすく同じ目線に立って物事に対応してくださり、とても良き出会いでした